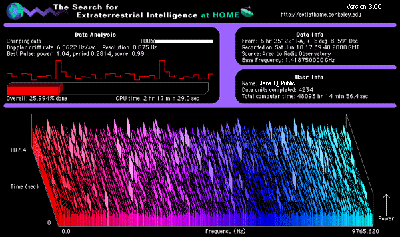
SETI @ Home
2004.02.15
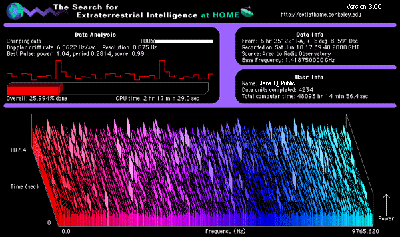
SETI @Home(セチ=地球外知性探査計画)が話題に上ったのは1999年5月のことだ。 MacWire (だったと思う)で紹介され、瞬く間に仲間内に広がった。
SETI@HomeにはUFOヲタクがほとんど参加していないのも好感が持てた。ベントラだの、信じる、信じないの話ではなく、科学的な分散解析プロジェクトという位置づけなのだ。本家のBBSに「政府に金がないんなら、オレたちが手伝ってやるよ」とスラングの米語で書かれていたのは感動ものだった。
何でこんなものが仲間うちで流行ったのか?今となってはよく思いだせない。新製品が出るたびに処理能力が上がっていくコンピュータの性能を計るのに「ワシの今度のMac、セチが6時間」とか「エーッ15時間もかかるん。遅っせー」という会話があいさつがわりに交わされていた。
解析数で順位がつくものだがら、解析したユニット数を競うようになるのに時間はかからなかった。ファイルサーバーはおろか、家中の Mac に 24 時間運転をさせるととんでもない電気代がかかり、早いマシンを使うとそれがまた電気を食う。家人にはすごく評判が悪かった。
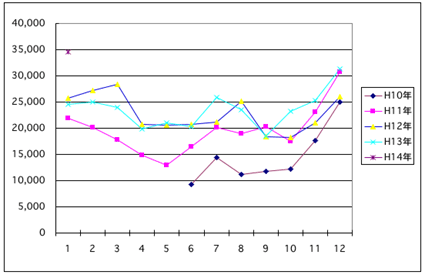
わが家の電気代の推移。ちなみに15年以降、電気代は減少している。
もともとは「使っていない時間、 CPU をボランティアで貸して欲しい」というプロジェクトなのに、本末転倒というか“セチる”ための連続運転もあちこちで見られた。心意気はよく判るが、電気エネルギーを浪費する、地球には全く優しくないプロジェクトだ。
これはわが家の1999年12月ごろの機器構成だ。
| PowerMacG4/450/DVD | 5h40m | OS9 |
| PowerMac5430/G3/300/1M | 8h30m | OS8.5.1 |
| PowerMac8600/G3/250/1M | 9h50m | ASIP 6.2 |
| PowerMac9500/G3/400/1M | 7h40m | OS X Server |
| PowerBookG3/400/1M | 8h | OS9 |
| iMacDV SE/400 | 11h | OS9 |
| iMac | 14h | OS8.5.1 |
最も時間がかかったマシンは、当時持ち歩いていた PowerBook1400c。G3プロセッサーに換装しているにも関わらず、1ユニットの処理に27時間もかかる代物だった。
スクリーンセーバーで3D迷路を描かせたり、おねーさんの水着姿を出そうものなら、「そんなことに貴重なCPUパワーを使うな。人類に貢献できることもあるぜ」となかば本気で怒りだすヤツまで現れた。
逆フーリエ変換の演算にはそのテーブルを広げるCPUの2次キャッシュの容量がものを言うとか、複数のSETIをマルチタスクで走らせるなど、いろんな情報がまことしやかにネット上を流れていた。RISCプロセッサの性能とか、PentiumのXEONのキャッシュの効果を思い知らされた記憶がある。
なんとか最初の1年で4900ユニットを達成。毎週ほぼ100ユニットの計算をさせた。毎日14〜15ユニットだ。よくこんなことしたよなぁと思う。
処理プログラムが ver.3 に上がった際、解析方式が変わったため、せっかく5時間台まで上がっていた解析時間が2倍以上かかるようになった。こうなると処理ユニット数はかせげない。仲間内からも脱落者(失礼!)が出たし、個人宅でフル稼働というのも電気代から台数を絞るようになった。個人ができる範囲での協力ということだ。
2004年2月15日現在、寺沢屋は解析ユニット数21324(!)、トータル CPU 時間32年(!)、平均処理時間13時間7分。約488万ユーザー中5284位だ。
日本国内では約16万ユーザー中268位。
機器更新のままならない、個人としては健闘しているほうだろう。
参加者の多くは、こんな短いスパンではおそらく何も成果がないということに気付いているのだ。万が一にも何か出てくれば、地球外知性の共同発見者(のひとり)として、人類史上に永遠に名前が残るだろう。
当時、仲間とよくこんな話をしていた。
ある日、星条旗を立てた黒塗りのリムジンが突然わが家へやってきて、降りてきた大使館員に「合衆国大統領が会いたいと言っている。専用機を用意しているので来ていただきたい」と、有無を言わせずワシントンD.C.に連れて行かれる。(こりゃ、映画「アルマゲドン」の話だ)
なんてことにはならないだろうけど、招待されて「リンカーンの間」に1泊ぐらいはさせてくれるだろうか。ワシとしてはごほうびに米海軍のF/A-18ホーネットの後部座席に座って飛んでみたい。これぢゃ、ガイ・カワサキだな。
(了)